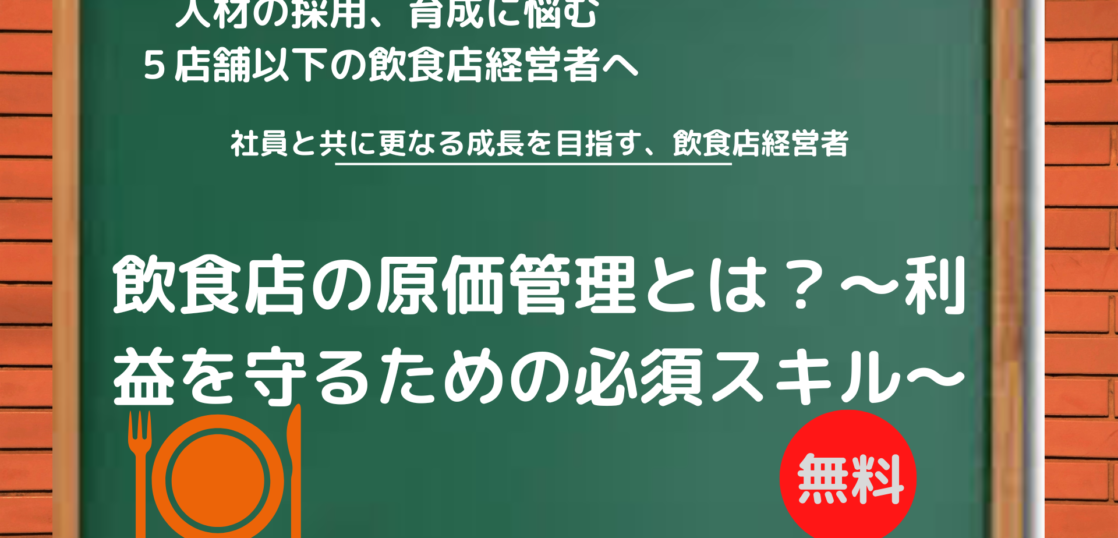この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
飲食店の原価管理とは?〜利益を守るための必須スキル〜
飲食店の経営において、「原価管理」は利益を生み出すための生命線とも言える業務です。原価とは、料理や飲み物を提供するために必要な食材費や材料費のこと。売上が好調でも、原価をコントロールできなければ、利益は簡単に失われてしまいます。
原価率の目安とその重要性
一般的な飲食店では、原価率(=原価 ÷ 売上)は28〜35%が理想とされています。たとえば、1,000円の料理を提供する場合、食材コストは280〜350円が目安です。これを超えると、人件費や家賃、光熱費などを差し引いた後に利益が残りにくくなります。
原価管理の具体的な方法
効果的な原価管理には、以下の3つのステップが重要です。
-
仕入れの最適化
複数業者との価格交渉や、季節の食材の活用によりコストを抑える。 -
食材ロスの削減
適正在庫の管理や仕込みの工夫により、廃棄ロスを減らす。 -
利益を意識したメニュー設計
「高原価=高価格」ではなく、「満足感のある低原価メニュー」や、原価率が高くても回転率の高い看板商品をバランスよく構成する。
なぜ今、原価管理がより重要なのか?
近年は物価高騰や人件費の上昇により、店舗経営のコスト構造が変化しています。こうした中で、原価を「感覚」ではなく「数値」で管理することが、持続可能な経営には不可欠です。
まとめ
原価管理は、単なるコスト削減ではなく、価値ある商品を適正な価格で提供しつつ、利益を確保するための戦略的な取り組みです。数字に強い店長こそが、強い飲食店をつくるのです。
以上がチャットGPTに問うと答える答えです。
どうでしょうか?
理解出来ますか?皆さん知っている事だと
思います。
この文面では、最も重要な視点が
抜けています。
それを追記しますね!
原価管理の定義は、
『標準原価と実際原価の差異の管理』
であります。
*標準原価=レシピ原価の出数総計
*実際原価=棚卸し後の原価
標準原価=レシピ上の原価ですが、
更に詳しく言うと、お客様に提供する価値と
その結果、店舗が得る利益、双方を考えた原価
と言う事です。
御社には、
1、全商品のレシピは存在しますか?
2、その一覧表で出数を入れ、月次の標準原価
を毎月算出してますか?
3、棚卸し作業を毎月実施してますか?
4、その差率、差額を出してますか?
この4点チェックです。
その上で、差率から差額を出す、
即ち、差率*売上が差額です。
例えば
売上800万円で差率が1%とすると
差額は、8万円となります。
更にその差額を高額仕入れ商品の個数に
置き換えるとリアル感が増します。
原価ロス1%とは、8万円
8万円とは、生ビールの樽8本分です。
1ヶ月で生樽8本分と言うと、リアル感が
増すと思います。
以上
原価管理についてです。